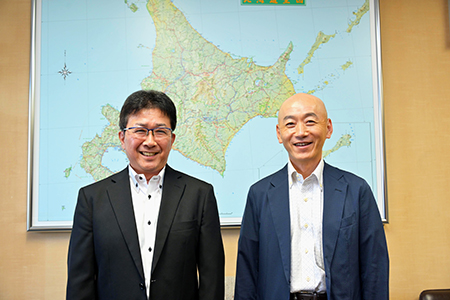国土交通省北海道開発局様はDREPスタート時からプロジェクトメンバーとしてご参加頂き、また組織として積極的にDREPを受講くださっています。今回は受講を推進・管理いただいている米元氏にお話をお聞きしました。
※このインタビューは2024年10月~2025年9月に提供されたPhase2を受講された方に伺いました。これらのご意見を反映し、2025年10月からPhase3の提供が始まっています。
(2025年7月10日 国土交通省北海道開発局にて)

国土交通省北海道開発局
事業振興部技術管理課長
米元 光明 氏
現場からDX推進と人材育成の最前線へ
北海道開発局・米元氏が語る、38年のキャリアとこの先の課題
「昭和63年に北海道開発局へ入局し、河川・ダムの設計・積算や監督などの現場業務から、本部での計画系業務、所長職を経て、現在はDXや働き方改革に取り組んでいます。」河川整備計画の策定では本省との折衝、網走での事業では地元漁協との調整や生態系保全など難しい問題解決を経験したそうです。近年は石狩川中流部・北村遊水地整備でも長期間にわたる地元との協議に尽力されてきました。長いキャリアを積んだ現在もなお、土木業界の未来を見据えた取り組みを続けています。
「人が減っているときに休みを増やすという、ある意味真逆の改革を進める必要がありました。そこにDREPによる人材育成に出会えて、やるべき改革の道筋が明確になり本当に幸運でした。」
人材育成と組織の温度差
DREPでデジタル人材の底上げ
「言葉だけが先行しICT・DXが十分に理解されずに、実際に使える人が少ない現状を少しでも改善することが建設業の課題でした。我々の組織自体もデジタルリテラシーを底上げし、デジタル人材を育成する必要があるため、DREP研修を導入しました。高齢層の抵抗感や部署間の温度差はもちろんありますが、組織全体の底上げができれば、少しでも前に進んでいくのではないか。」と、米元氏は話します。
「若い世代は相当能力が高いと思います。うちの課にもいますが何でも知っているし、色々教えてもらうこともある。我々世代も共通言語で話せるように勉強しなければ、彼らの足を引っ張りかねません。」さらに、「レベル差の大きい職員が一堂に学ぶと理解のロスが大きいので、まずは共通言語を浸透させることで集団研修の効果を高め、去年と今年、そして来年と、少しずつステップアップしていければと思います。」
広がるDREPの価値
できる人を尊重する風土へ
「なかば強制的に受講してもらった管理職など、研修の全課程を修了できなくても、デジタルの難しさを知ることで、できる人材を尊重する風土が生まれる。自分は無理でも、若い世代の能力の使い道や生かし方が分かる。それだけでもDREPを受ける価値はあります。」さらに、「今後はもっと若い世代や知識のある人がDREPを受講していくので、また違う成果や効果が生まれるでしょう。」と米元氏は期待を寄せています。
続いて、DREPを率先して受講いただいき、Stage4にも参画いただいている財津氏にお話をお聞きしました。

国土交通省北海道開発局
事業振興部都市住宅課長
財津 知亨 氏
デジタルの可能性
30年のキャリアを持つ財津氏が語る、災害対応の記憶と都市住宅分野への挑戦
平成7年に北海道開発局へ入庁し、今年で30年のキャリアを持ち、河川分野を専門としてきた財津氏は、道内の治水事業に主に従事してきましたが、九州・武雄河川事務所勤務時代に豪雨で川が越水し、災害対応に奔走した経験が今も記憶に残ると言います。現在は都市住宅課長として、道内自治体のまちづくりや住まいづくりの支援に携わっています。
「専門は河川なので、現在の都市住宅分野は専門ではなく、CopilotやChatGPTを使って専門用語などを調べることがよくあります。」
デジタルは不可避の時代
効率化のために使わざるを得ない
自身がパソコンやインターネットを本格的に使い始めたのは平成10年頃で、以降検索機能の向上、スマートフォンの普及、コロナ禍でのテレワーク・ウェブ会議の浸透などにより仕事のスタイルは大きく変わってきたと言います。「人口減少で人手が減る中、AIは便利なツール。効率化のためには今の時代、使わざるを得ないと思います。デジタル化が進む中、DREP研修で身につけた知識を共通言語として、若手職員とも違和感なく接する事ができる助けになっています。」
DREP研修の可能性と課題
北海道におけるデジタル活用の重要性
「令和5年に始まったDREP研修は非常にありがたい取り組みです。ただ、社会人が仕事をするうえで必要なデジタルの知識と研修の中味がまだフィットしていない部分もあり、そこが改善されれば更に受け入れやすくなると思います。あまり時間をとられない研修でよりわかりやすい構成や、業務と直結するような内容が、DREP普及の鍵になると思います。」さらに、「特に北海道は面積が広く、人口密度が低いので、デジタルを導入し、活用するメリットが大きいのでは。」と財津氏は感じています。
DREPステージ4への思い
デジタル活用で更なる業務効率化の実現へ
財津氏からはDREP Stage4(地域課題解決演習)受講のご希望があり、開発局の有志と共に演習を始めていただいています。課題は「行政におけるAIの活用」です。
「前職の技術管理課では、全道からの工事等の基準や要領に関する問い合わせに少人数で対応しており、機械が即答できればいいよねと話していた。」と言います。
「ChatGPTに関する講演を聴いた際に衝撃を受けました。農業革命、産業革命、情報革命に次ぐ大きな革命だと思いました。現在の都市住宅課で、情報セキュリティの制約が少ない範囲でまずは課内の効率化を試行しようと考えています。これが今回Stage4にチャレンジしようと思った背景です。」
デジタル活用のこれから
正しく理解し、次の段階へ
AIは高速で答えを返しますが、誤りもあります。「DREPの研修内容にもあるように、AIやデジタルの特徴を正しく理解した上で業務効率化につなげることが重要です。Stage1~3で基礎を学んだ上で、私どもの取組に続く、Stage4の第二弾、第三弾が出てくれば、と思っています。」と、冷静な視点で語ってくれました。